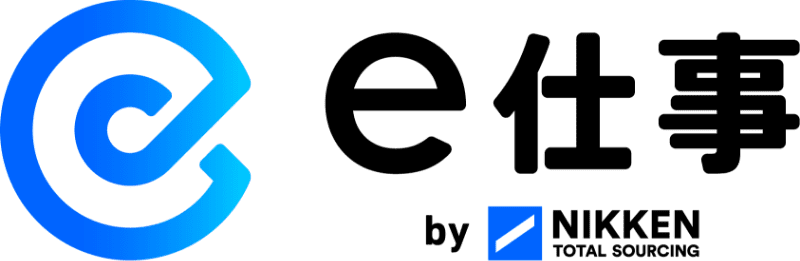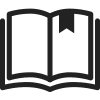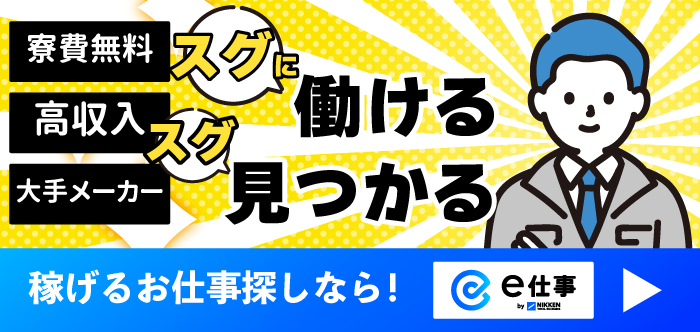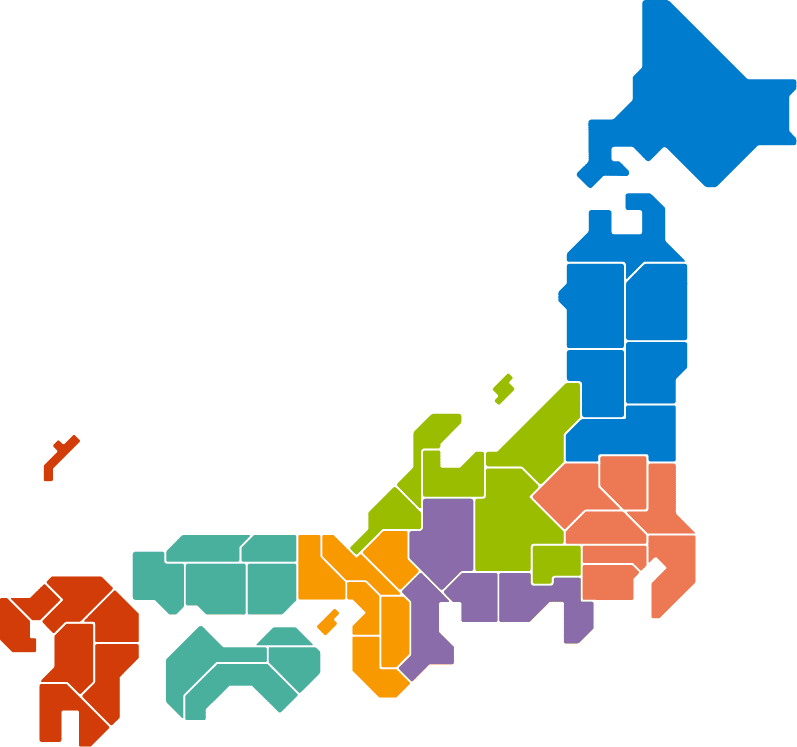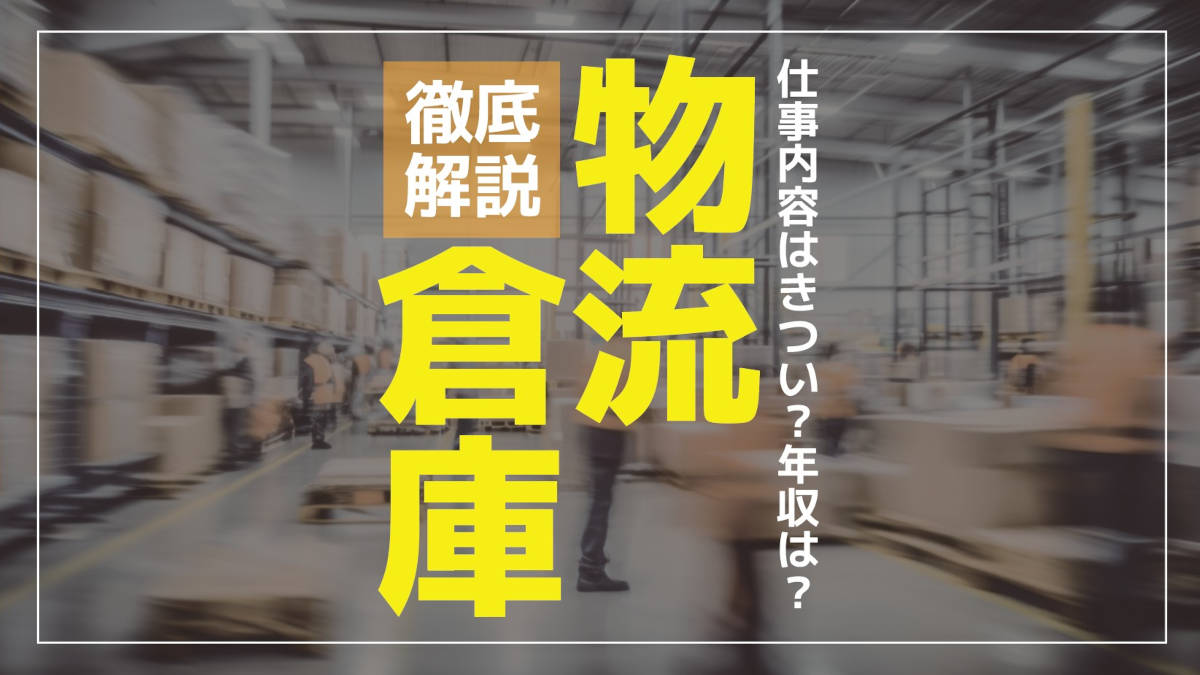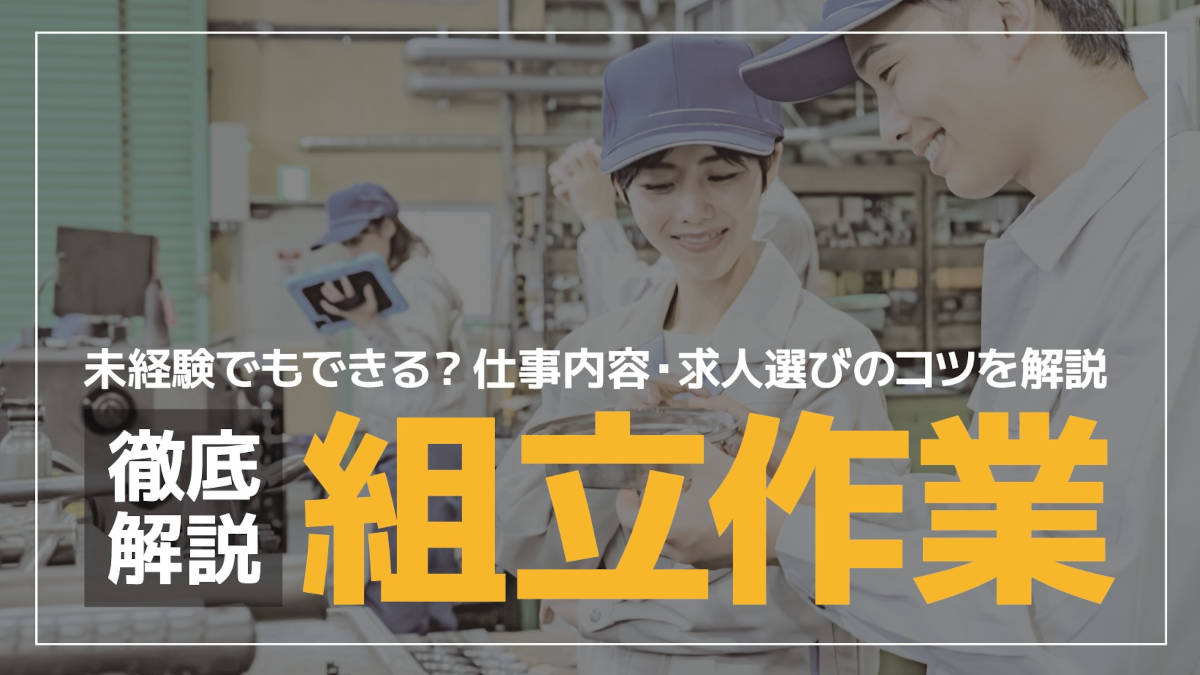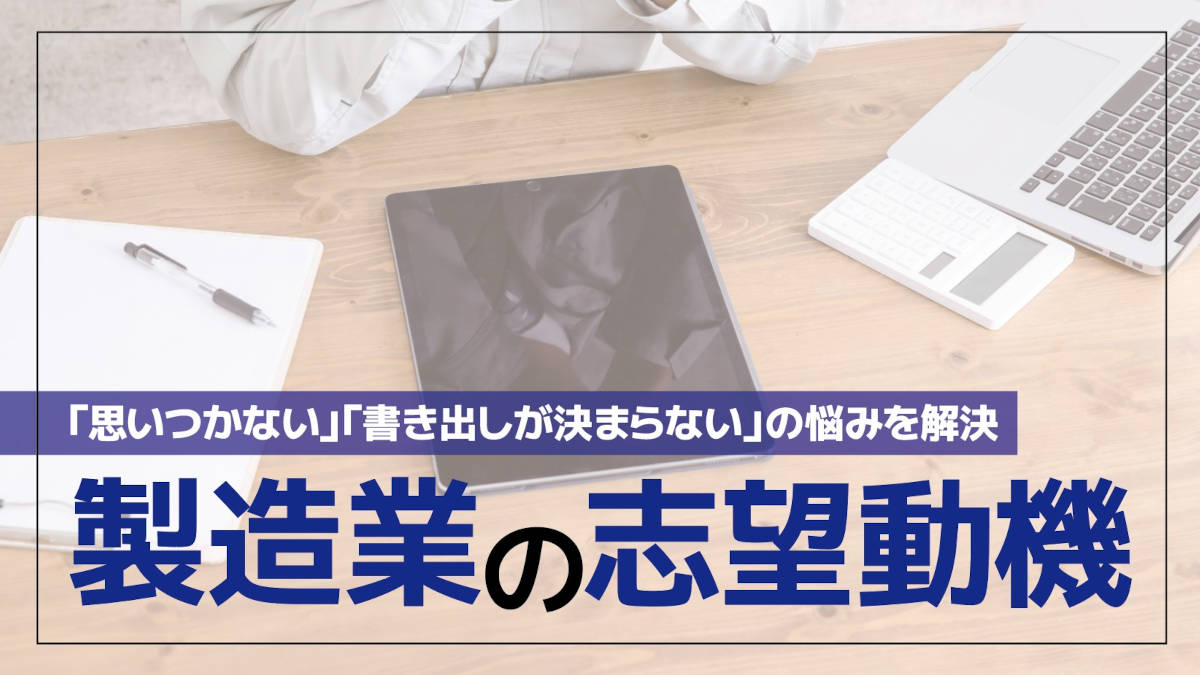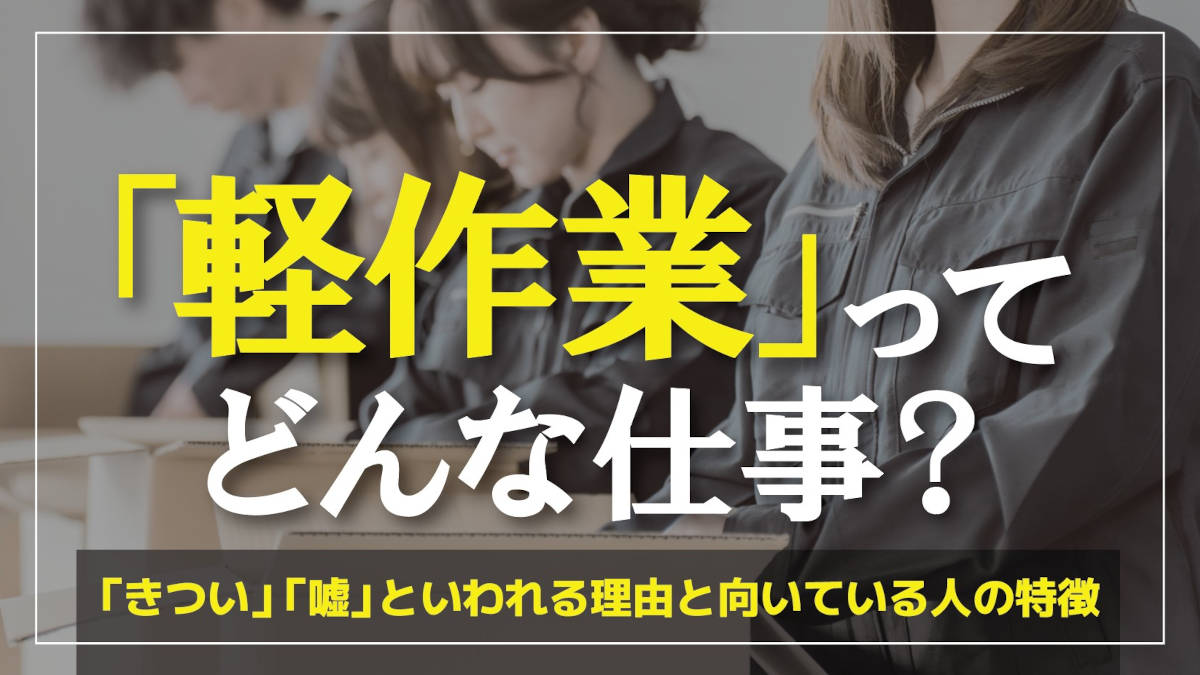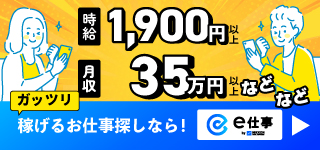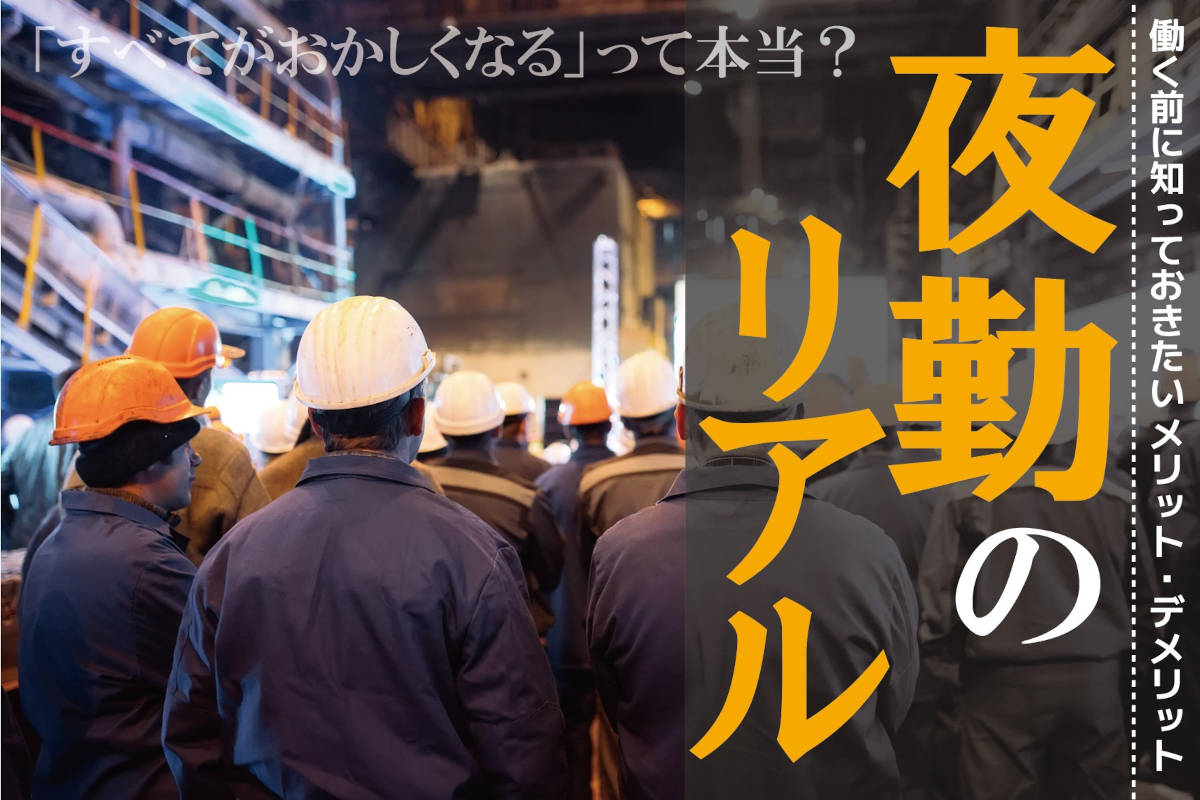
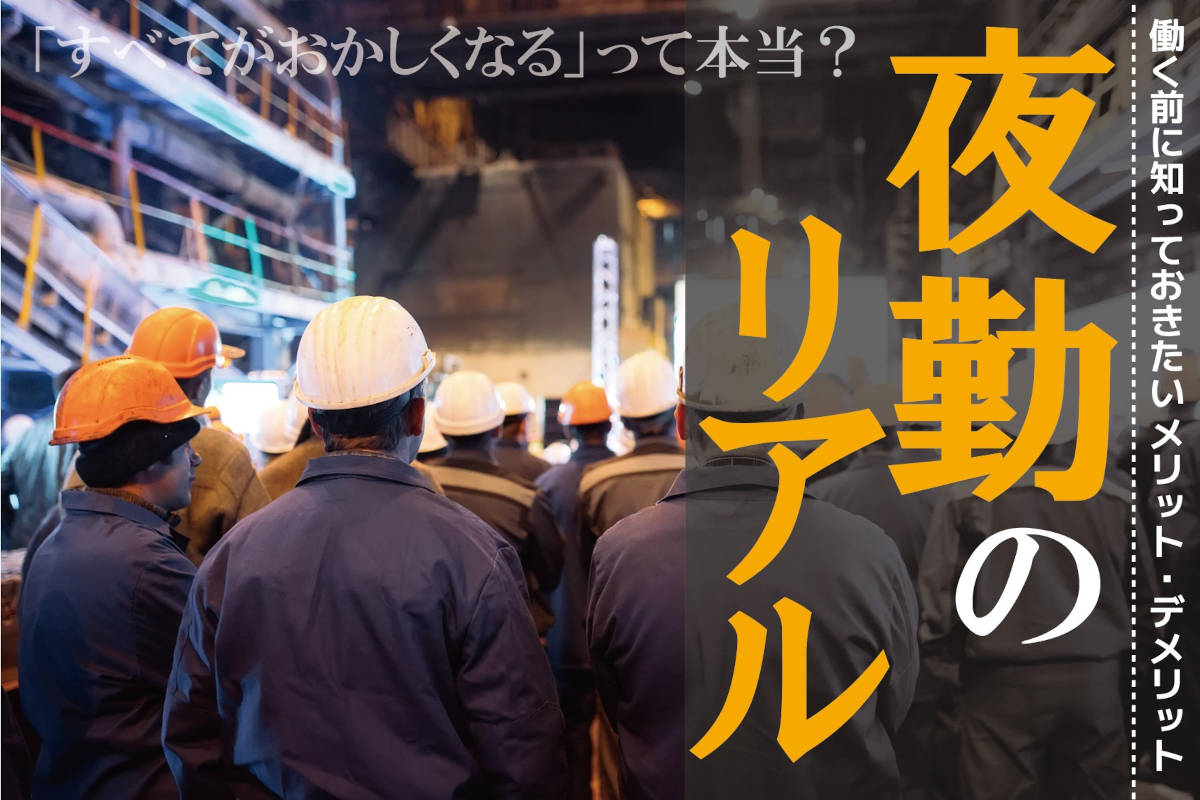
夜勤とは何時から?「すべてがおかしくなる」って本当?工場・製造業で働く前に知っておきたいメリット・デメリット
2025/08/04
「夜勤って、やっぱりきついのかな?」「すべてがおかしくなるって聞くけど本当?」――これは製造業や工場への就職・転職を検討する、多くの人にとって気になるテーマでしょう。夜勤には給与面の優遇など一定の魅力がある一方で、生活リズムの乱れや体調面の負担といった懸念が避けられないからです。
本記事では、夜勤の勤務時間帯や制度上の定義から、実際のメリットとデメリット、夜勤中の過ごし方や注意点まで、実務に即した観点から整理して解説します。夜勤に対する理解を深め、自身にとって「納得できる働き方」を選ぶための参考にしてください。
夜勤とは?基本の定義と時間帯
「夜勤」という働き方は、単に「夜に働く」というだけではありません。法律的な定義や勤務実態において、明確な特徴がある働き方です。
特に製造業や工場勤務などでは、夜勤シフトが組まれる理由や、該当時間帯のルールを正しく理解することが、就業前の不安を減らす第一歩となります。
まずは労働基準法上の「深夜労働」の定義と、実際の現場で用いられている夜勤時間のパターンを整理し、「制度としての夜勤」と「現場での夜勤」の違いについても触れていきます。知らずに働き始め、「思っていた内容と違った」とならないよう、夜勤の基本から丁寧に押さえていきましょう。
夜勤って何時から何時まで?労働基準法による定義
法律上、夜勤とは「午後10時から午前5時まで」の時間帯に労働を行う勤務を指します。この時間帯は「深夜業」として扱われ、割増賃金の支払いが義務づけられています。
| 時間帯 | 午後10時(22:00)〜午前5時(5:00) |
|---|---|
| 割増賃金の割合 | 基本給の25%以上(最低基準) |
| 適用対象 | 上記時間帯に1分でも労働があれば対象 |
ただし、「21時〜6時」「0時〜9時」など、夜勤の定義時間と実際の労働時間が異なる現場は多々あります。つまり、制度上の「夜勤」と、現場での「夜勤シフト」は必ずしも一致しないことを理解しておくことが重要です。
工場・介護・警備など夜勤のある職場とは
「夜勤がある職場」は限定されているものではなく、むしろ多くの業種で必要とされている働き方です。特に次のような業界では、24時間体制での対応が求められることが多いため、夜勤シフトが多く見られます。
【夜勤が多い職種・業界の主な例】
- 製造業・工場:ラインを止めずに生産を続けるため、日勤夜勤の交替制が基本
- 介護・医療:利用者や患者を24時間体制でケアする必要がある
- 警備・交通・運送:深夜の巡回、施設管理、配送業務など夜間業務が発生
- インフラ保守:電力・通信など、夜間でも安定稼働が求められる分野
こうした職場で夜でも働いてくれる人が、社会全体を支えているともいえます。つまり夜勤という働き方は決して特殊なものではなく、「誰かの暮らしを守る」責任ある選択肢として機能しているのです。
メリットとデメリットから見る夜勤の実態

夜勤は「手当が出て稼げる」という印象がある一方で、「体がきつい」「生活が不規則になりそう」と不安を覚える人も少なくありません。
ここでは、夜勤のメリットとデメリットを項目ごとに整理しながら、実際に働いたときに感じる可能性のある「実態」を明らかにしていきます。
夜勤で得られるメリット
「避けるべき働き方」と思われることもある夜勤ですが、実際にはメリットも数多く存在します。収入面だけでなく、環境面や時間の使い方など、人によっては日勤よりも働きやすいと感じることもあるでしょう。
ここでは、夜勤の代表的なメリットを次の4つの視点から考察します。
- 通勤ラッシュを避けられる
- 時給が高く、夜勤手当が加算される
- 人が少なく、静かで作業に集中しやすい
- 昼間の時間を有効活用できる
時給が高く、夜勤手当が加算される
夜勤の最大のメリットに挙げられるのは、やはり収入面における優遇でしょう。
法律で定められた深夜労働(22時〜翌5時)には、基本給の25%以上の割増賃金(深夜割増賃金)が義務づけられています。これがいわゆる「夜勤手当」のベースです。加えて、企業によっては独自の夜勤手当(固定額や時間数連動)を支給しているケースもあり、日勤と比べて1時間あたりの賃金は明確に高くなる構造があります。
夜勤と日勤の収入差をシンプルに比較してみましょう。
| 勤務形態 | 時給(例) | 割増・手当 | 実質時給(目安) |
|---|---|---|---|
| 日勤(通常) | 1,100円 | なし | 1,100円 |
| 夜勤(22時〜5時) | 1,100円 | 深夜割増25% → +275円 | 約1,375円 |
| 夜勤(+独自手当) | 1,100円 | 深夜割増+夜勤手当(例:+200円) | 約1,575円 |
このように、同じ作業時間でも実質時給は大きく異なり、月数万円単位で収入差が出る可能性があることから、特に短期間で稼ぎたい人にとって、夜勤は非常に有利な働き方となり得ます。
ただし、手当の有無や計算方法は企業によって異なります。求人票や労働条件通知書での明記を必ず確認しましょう。
人が少なく、静かで作業に集中しやすい
日勤帯に比べて、夜勤は職場全体の人数が少なくなる傾向です。そのため人間関係の煩わしさや職場の騒がしさが軽減され、業務に集中しやすい環境が整っています。
特に、製造ラインや清掃業務など、黙々と作業することが求められる仕事においては、夜勤のほうが適していると感じる人も少なくありません。静かな空間で落ち着いて働きたい人にとって、大きなメリットとなるでしょう。
昼間の時間を有効活用できる
夜勤明けの昼間の時間をどう使うかによって、生活の充実度は大きく変わります。たとえば役所など、主に平日の日中しか対応していない施設も、夜勤勤務であれば問題なく利用できます。また、昼間に子どもと過ごせる、習い事や副業に取り組む時間を確保できるといった点も、人によっては大きなメリットです。
「働きながらプライベートの自由度も確保したい」と考える人にとって、夜勤は柔軟なライフスタイルを実現しやすい働き方のひとつになります。
通勤ラッシュを避けられる
夜勤シフトの多くは、日中の通勤時間帯を避けた勤務スケジュールになっています。そのため、満員電車や渋滞といった通勤ストレスから解放されやすいことも夜勤ならではの利点です。
特に都市部では、通勤ラッシュの影響で毎日大きなストレスを感じるケースは少なくありません。穏やかな生活リズムを求める人にとって、これは見逃せないポイントです。
夜勤のデメリットときつさ
夜勤には複数のメリットがある一方で、身体や生活リズムにかかる負担は無視できません。特に長期的に夜勤を続ける場合、健康管理や社会的なつながりに影響がおよぶことも懸念されます。
ここでは、夜勤に伴う主なデメリットを次の4つの観点から具体的に整理していきます。
- 生活リズムが崩れやすく、体調管理が難しい
- 家族や友人との時間が合わなくなる
- 夜間は判断力が鈍り、事故リスクが上がることも
- 仮眠や休憩が取りづらい職場もある
生活リズムが崩れやすく、体調管理が難しい
夜間に働き、昼間に眠るという生活は、本来の人間の生体リズムとは異なります。これにより、自律神経やホルモンのバランスが乱れてしまうと、慢性的な疲労や睡眠障害、消化不良、免疫力の低下といった影響も懸念されるでしょう。
特に夜勤明けに十分な休息が取れない日が続くと、体調を崩すリスクは高まります。夜勤を選ぶ際は、生活リズムを整える意識的な工夫と自己管理が不可欠です。
家族や友人との時間が合わなくなる
夜勤は一般的な日中の活動時間とずれるため、家族や友人と過ごす時間が取りづらくなります。
こうした「周囲と時間が合わない」というストレスは見過ごされがちですが、長期間にわたる勤務では精神面にも大きな影響を及ぼしかねません。周囲の理解とサポート、そして自分自身の生活設計が求められます。
夜間は判断力が鈍り、事故リスクが上がることも
深夜帯は身体が本来休息を求める時間であるため、集中力や注意力の低下を招くこともあります。これにより、機械の操作ミスやヒューマンエラーといったリスクの高まりも懸念されます。
特に製造業や運送業など、物理的な危険が伴う現場では、「疲労の蓄積=安全性の低下」という直接的な因果関係を理解しておかなければいけません。安全対策と適切な休憩がとれる環境かどうかは、職場選びの重要な判断基準となるでしょう。
仮眠や休憩が取りづらい職場もある
業務の性質によっては、仮眠や休憩の時間が確保しづらいケースもあります。特に介護や警備のように突発的な対応が求められる職場では、長時間にわたって緊張状態が続くことで、身体の疲労や精神的なストレスが蓄積しかねません。
仮眠スペースの有無や、休憩時間の制度が明確に定められているかなど、職場環境の確認は夜勤において重要な観点です。
夜勤生活の過ごし方・体調管理の工夫

上述したメリットとデメリットを勘案すると、夜勤に慣れていく過程で最も重要になってくるのが、生活リズムの整え方と体調管理の工夫です。
夜間勤務には独特のペースがあります。それを無理なく継続するには、日常のちょっとした選択や行動の積み重ねが重要になるでしょう。ここでは、夜勤明けの過ごし方や、勤務中に心がけたいポイントを紹介していきます。
夜勤明けの過ごし方・仮眠や食事のポイントを意識
夜勤明けは、心身の疲労が蓄積しているタイミングです。「帰ったらすぐに寝たい」――これは多くの夜勤経験者が抱える本音であり、そのまま長時間眠ることが理想にも見えますが、実は「寝すぎ」が次の夜勤に悪影響を与える可能性があることも考慮しましょう。
夜勤では、生活リズムを保ちつつ体を休めるための現実的な工夫が求められます。
【夜勤明けの過ごし方のコツ】
- 仮眠は90〜180分を目安に:長すぎると次の夜勤で眠れなくなることも。リズムを保つなら短め睡眠が◎
- 帰宅後は入浴 or シャワーを軽く浴びてリラックス:汗や疲労を流すことで、入眠の質も向上
- 朝食は消化のよい軽食で:温かい味噌汁やおかゆなど、胃腸にやさしいものを選ぶ
- 「昼でも夜のような環境」を整える:遮光カーテンや耳栓で、外光や生活音をシャットアウト
また、起床後には軽いストレッチや散歩を取り入れると、生活リズムのズレを軽減できます。こうした自分なりのルーティンをつくることが、心身の回復とリズム維持の鍵になります。
夜勤中の体調管理と快適な過ごし方
繰り返しになりますが、夜勤とは身体が本来眠るべき時間に働いている状態です。集中力や判断力の低下を最小限に抑えるために、事前の準備と勤務中の小さな工夫を意識しましょう。
【夜勤中の体調管理ポイント】
- 開始前に軽く食事をとる:エネルギー切れを防ぐため、出勤前の「軽食」は必須
- こまめな水分補給を忘れずに:眠気・倦怠感の原因にもなるため、意識して水分をとる
- 冷え対策に羽織物やひざ掛けを用意:夜間は体温が下がりやすいため、冷えすぎ防止が重要
- 休憩中に短時間の「目を閉じる時間」を取る:眠れなくても、5〜10分間目を閉じるだけで回復感がある
- 勤務後のカフェイン摂取は控えめに:帰宅後の入眠に支障をきたす可能性があるため注意
また、職場のルールに沿って仮眠を取れるかどうか、勤務環境が整っているかを事前に確認しておくことも、夜勤を継続する上での重要なポイントです。
まとめ
夜勤という働き方には、日勤にはないメリットと独自の課題が存在します。たとえば割増賃金による収入アップ、静かな職場環境、昼間の自由な時間。これらは一定の条件を求める人にとって魅力的な要素です。
その一方で、生活リズムの乱れや健康面のリスクといった側面も無視はできません。つまり、夜勤の向き・不向きは「何を優先するか」によって大きく変わるということです。
- 短期間でしっかり稼ぎたい人
- 人間関係のストレスが少ない環境を望む人
- 日中の自由な時間を有効に使いたい人
こうした人にとっては、夜勤はむしろ「働きやすい」と感じられるでしょう。一方、生活リズムの乱れに弱い人や、家族との時間を大切にしたい人にとは、慎重な検討が求められます。
夜勤という働き方に対する理解を深め、自身にとってベストな選択肢を検討してください。
工場・製造業のお仕事探しは求人サイト「e仕事」がおすすめ!
工場・製造業のお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事」がおすすめ!
例えば
- 時給1900円以上
- 月収35万円以上
- 寮費無料
- 大手メーカー求人多数
など様々な求人があります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。
e仕事はこちらから↓↓↓
関連記事
求人カンタン検索
こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。
都道府県で探す
業種で探す
こだわり条件で探す
- 待遇
- 働き方
- 募集条件
- 職場環境