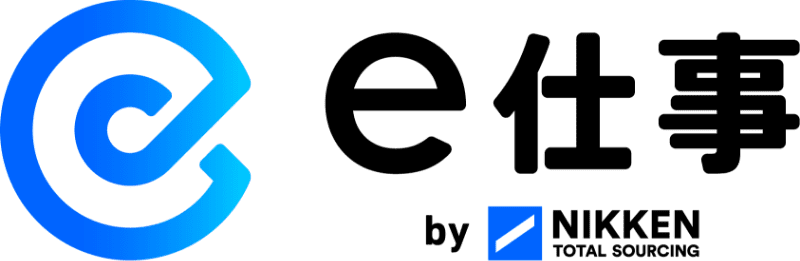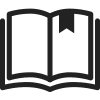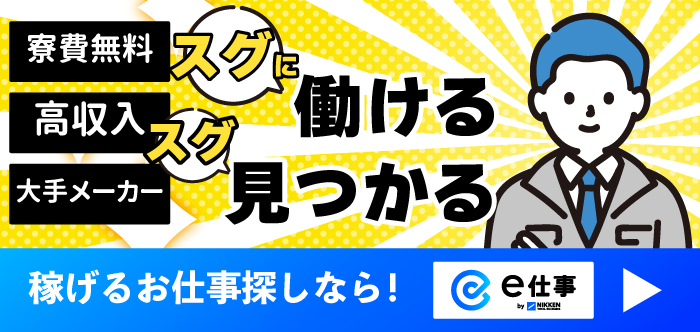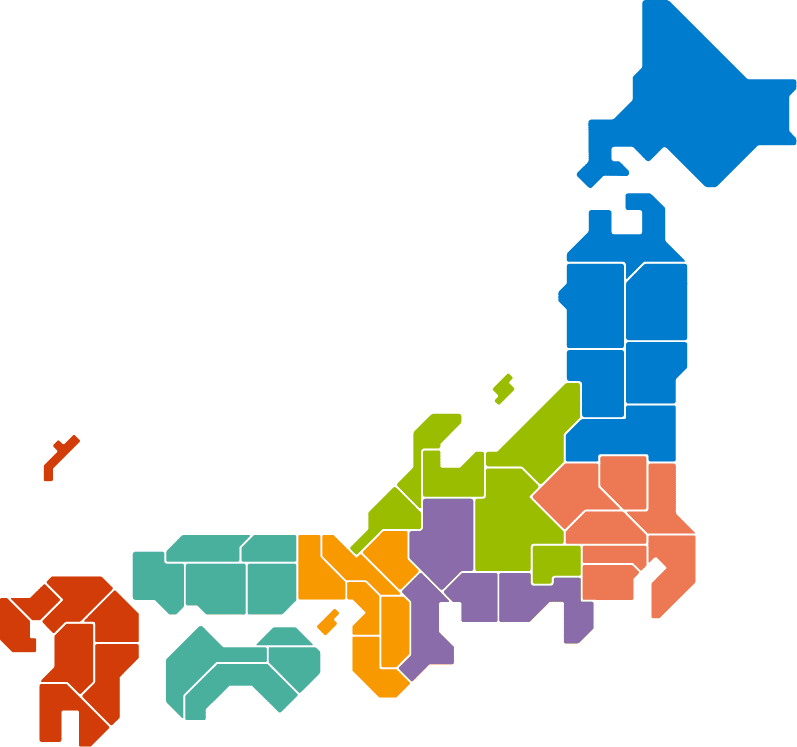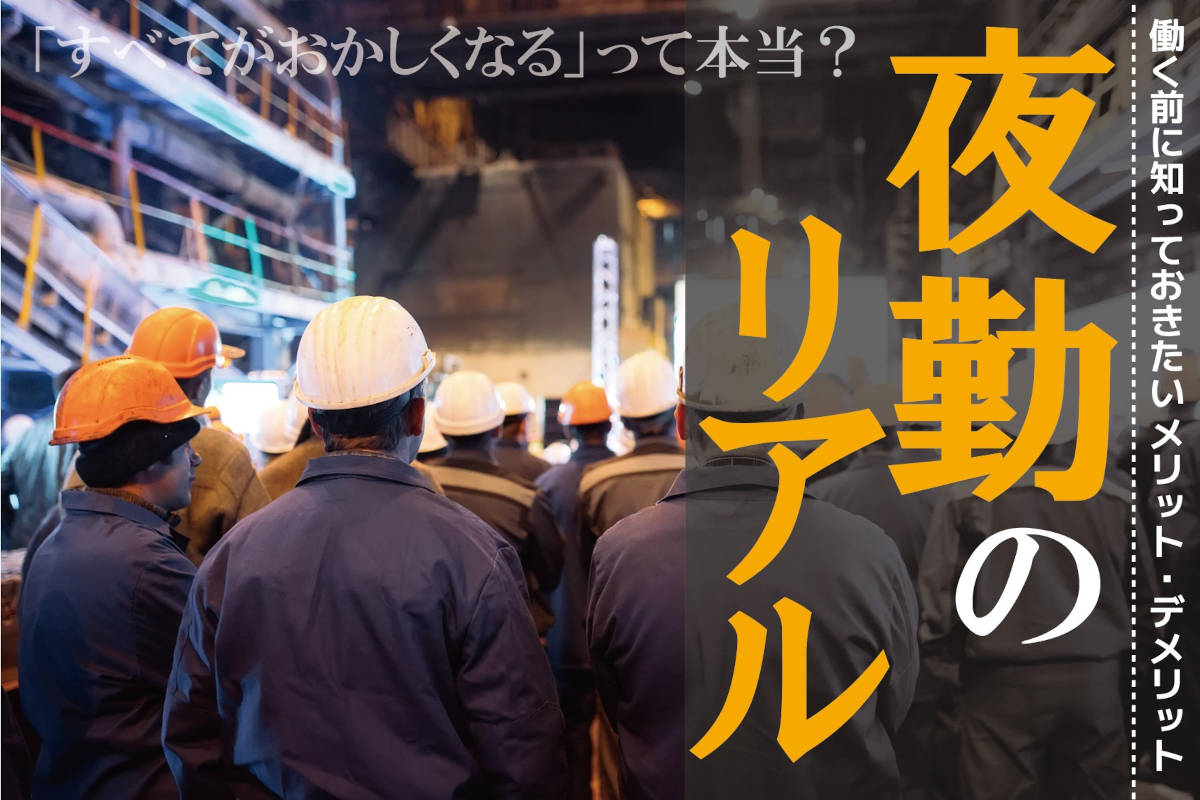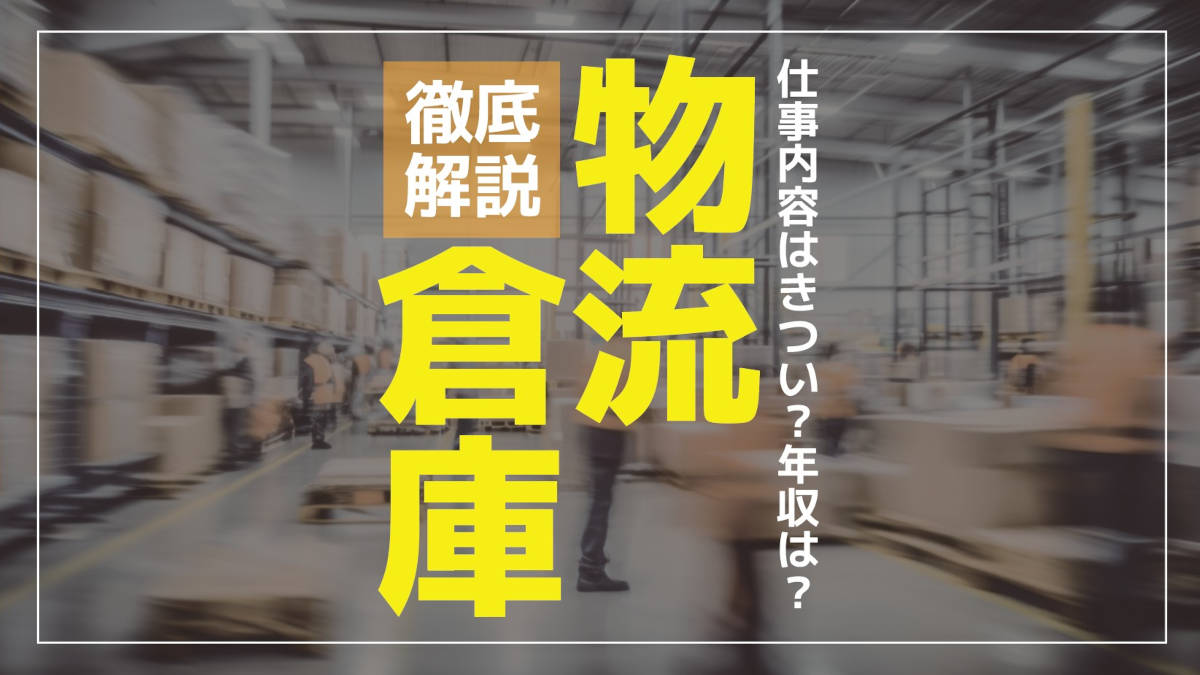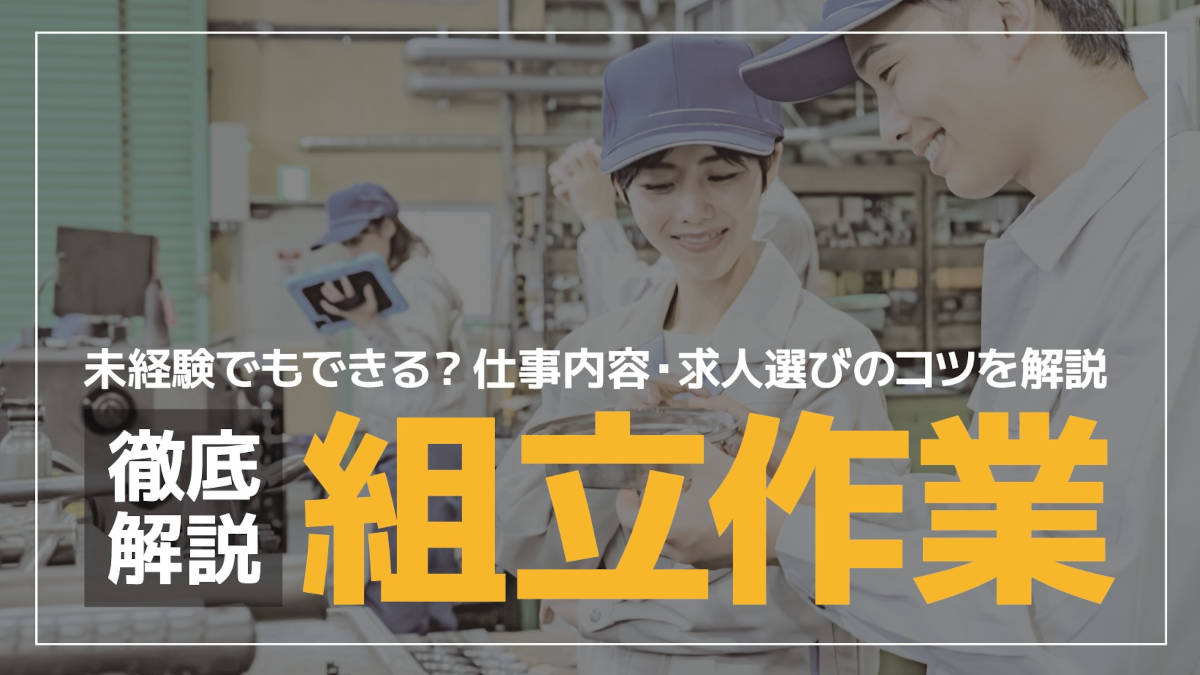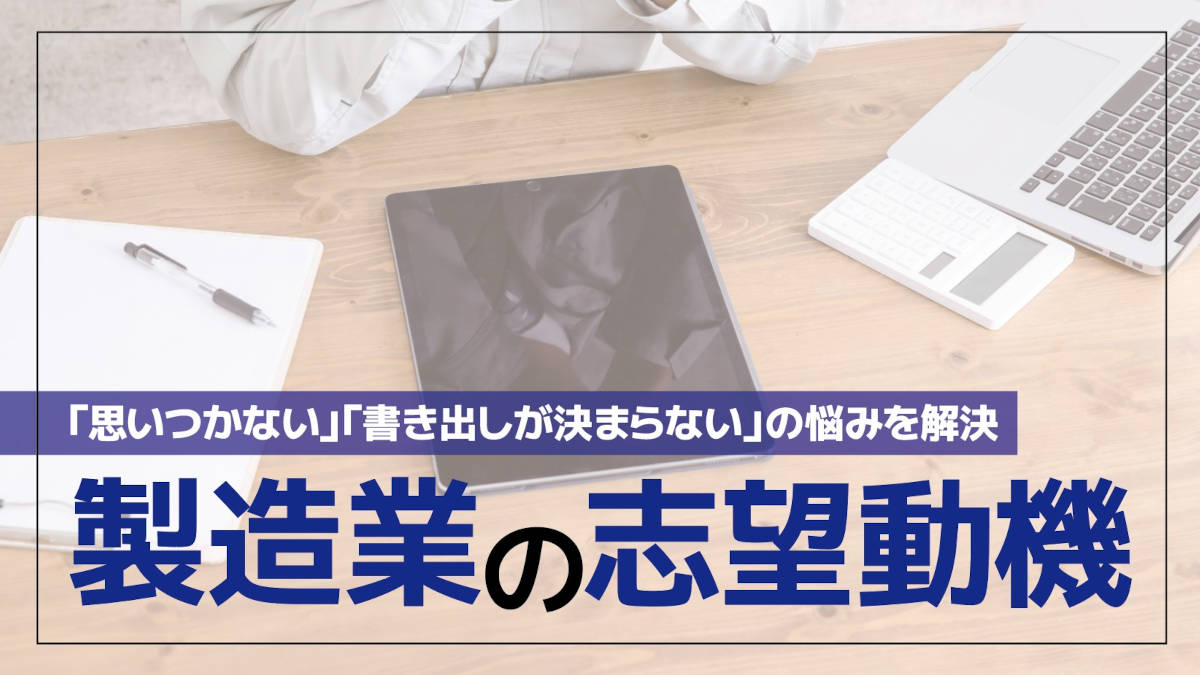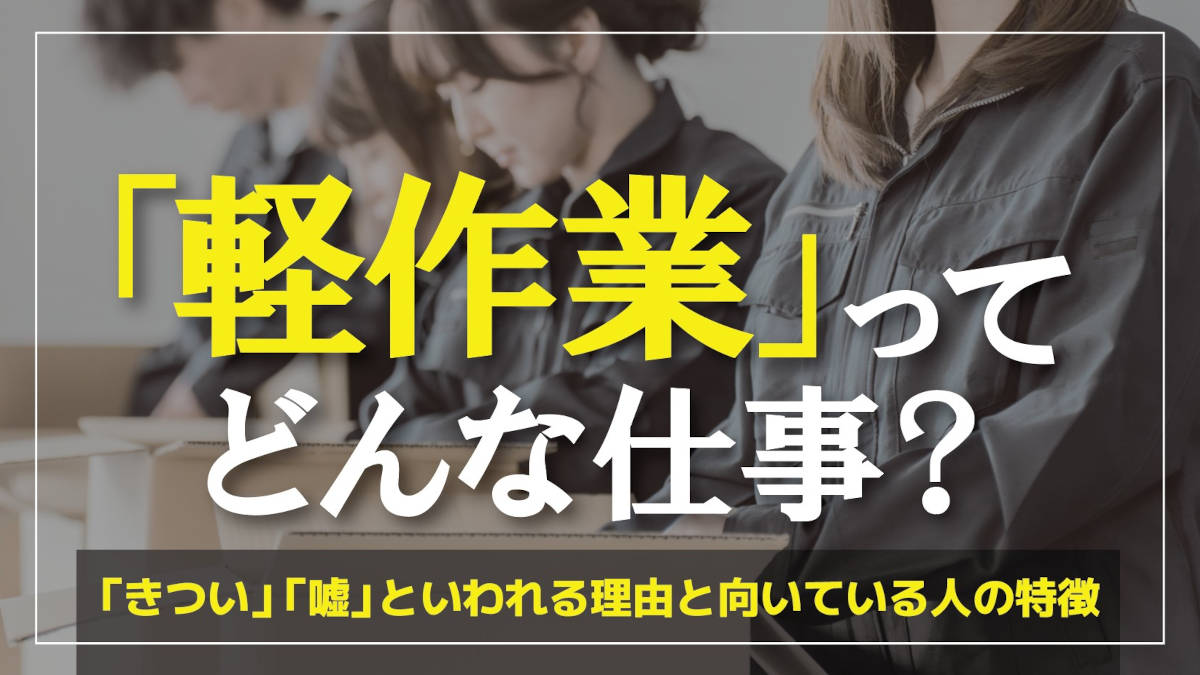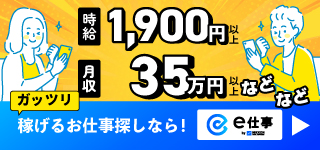工場の準夜勤ってきつい?勤務時間や手当、生活リズムなどメリット・デメリットを徹底解説
2025/08/08
「準夜勤って、どんな働き方?」「夜勤とどう違うのか、正直よくわからない」。製造業や工場での勤務を検討するなかで、耳にすることの多い、「準夜勤」の言葉。しかしその実態は、意外と知られていないかもしれません。
本記事では、準夜勤の勤務時間や役割、製造現場での位置づけなどをわかりやすく解説します。生活リズムや給与面のポイントも含めて働く前に知っておきたい情報を整理し、自身にとって「納得できる働き方」を選ぶための参考にしてください。
準夜勤とは?基本の意味と働き方

製造業や工場勤務の求人で見かけることの多い「準夜勤」という言葉。なんとなく「夜に働く」というイメージを持っている人も多いかもしれませんが、準夜勤は夜勤とは異なる、独自の勤務形態です。
まずは準夜勤の定義や代表的な勤務時間帯、製造業での導入理由、そして工場現場における具体的な職種や役割について整理していきます。準夜勤はどのような働き方で、どんな業務に携わることになるのか? 制度面だけでなく、現場での実態を含めて解説します。
準夜勤って何時から何時まで?日勤・夜勤との違い
「準夜勤って、夜勤とはちがうの?」――製造業・工場への就職や転職を考えている人にとって、まず気になるのはその「時間帯」と「働き方」でしょう。
準夜勤とは、夕方から深夜0時前後までの時間帯に勤務するシフトのことです。具体的には、次のような勤務時間帯が該当します。
【準夜勤の勤務時間帯の例】
- 15:00〜23:00
- 16:00〜0:00
- 17:00〜1:00
このように、日勤よりも遅く、夜勤よりも早い。そんな中間的な立ち位置にあるのが準夜勤です。夜勤と比べると深夜帯の労働が少ないため、体力面や生活リズムの観点から、無理なく働きやすいという声も多く聞かれます。
準夜勤が導入されている主な業界・職種
準夜勤は、特定の業界に限らず、24時間体制の業務が求められる現場で広く導入されています。たとえば、次のような職場が代表例です。
【準夜勤が多い職種・業界の主な例】
- 製造業
- 物流センター
- 医療・介護施設
- コールセンター など
特に製造業や看護師といった業界・業種では準夜勤を含む交代勤務制が定着しています。就業時間をずらすことで、限られた設備や人員を最大限に活用し、安定体制を維持しているのです。
製造業で準夜勤が求められる理由
製造現場に準夜勤が導入されている背景には、「生産性の安定」と「人員配置の柔軟性」があります。
たとえば自動車や電子部品の生産ラインでは、1日24時間の稼働が当たり前です。この稼働を止めず維持するために、日勤・準夜勤・夜勤といった形で勤務を分割し、3交代制が組まれる現場が多く見られます。
また、準夜勤は夜勤よりも生活リズムへの負担が少ないため、人材確保という面でも有効です。若年層や家庭を持つ求職者からは、「深夜まで働くのは不安だけど、日中は別の予定もある」といったニーズに応える選択肢としても機能しています
製造業・工場での「準夜勤勤務」のポジション
準夜勤のシフトが組まれる工場では、以下のような職務を任される傾向が多く見られます。
- 組立・加工業務
- 検品・検査スタッフ
- 自動機械のオペレーター業務
- 出荷前の梱包・準備作業
こうしたポジションは業務の手順やリズムが明確に決まっており、引き継ぎがしやすいという特性があります。準夜勤は「日勤帯の終わりを支える役割」や、「夜勤のスタートに備えた準備」を担うことも多く、工場の安定稼働に欠かせないポジションとなっているのです。
準夜勤の代表的な勤務時間パターン
上述したとおり、準夜勤は15時〜24時を中心とした勤務帯ですが、企業や業種によってさまざまなバリエーションがあります。以下、実際の工場などで採用されている代表的なパターンを示します。
| 勤務パターン | 備考 |
|---|---|
| 15:00〜23:00 | 比較的早めに帰宅できる |
| 16:00〜0:00 | 工場勤務で多い設定 |
| 17:00〜1:00 | 夜間帯との交差が大きめ |
なお、勤務時間帯によって深夜割増、そして企業が独自に設定する追加の手当である「夜勤手当」の対象可否が変わる点もポイントです。夜勤手当の取り扱いは就業先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
準夜勤の生活リズム【1日スケジュールの実例】
準夜勤の働き方は、日勤と夜勤の中間的なシフトであるだけに、生活リズムの整え方に若干の不安を覚える人も少なくないでしょう。特に初めて工場勤務を経験する方にとっては、「いつ起きて、いつ寝ればいいのか」「家事や食事のタイミングはどうするのか」といった疑問が湧いてくるのは当然です。
ここでは、準夜勤の1日の流れを具体的にイメージできるよう、代表的な勤務パターンをもとにした生活サンプルを紹介します。さらに、勤務明けの過ごし方やシフト切り替え時の注意点など、安定した生活を送るためのヒントも解説します。
準夜勤のある1日の流れ(15:00〜24:00勤務の例)
ここでは、準夜勤の典型的な勤務時間である「15:00〜24:00」を例に、1日の流れを追ってみます。
| 時間帯 | 行動内容 |
|---|---|
| 08:00〜10:00 | 起床、朝食、家事・私用など |
| 10:00〜13:00 | 自由時間(買い物、通院、役所手続きなど) |
| 13:00〜14:00 | 昼食・出勤準備 |
| 14:00〜15:00 | 出社・着替え・業務準備 |
| 15:00〜24:00 | 勤務(途中に休憩あり) |
| 24:00〜25:00 | 退勤・帰宅・軽食・入浴など |
| 25:00〜08:00 | 就寝(睡眠時間を確保) |
このように、午前中の時間を自分のために使えるのが準夜勤の大きな特徴です。銀行や役所などの窓口に行きたい場合などにおいても、日勤より融通がききやすい点がメリットになります。
準夜勤明けの過ごし方と睡眠リズム
準夜勤を継続的にこなすうえで大切なのが、勤務後の過ごし方と睡眠リズムの安定です。
勤務終了後の時間帯は、帰宅してからも神経が高ぶっていることが多いため、いきなり布団に入るのではなく、まずは軽い食事や入浴で気持ちを落ち着けるのがポイントです。
また、睡眠時間は深夜から朝にかけて確保するのが一般的ですが、日差しや生活音の影響で熟睡しづらいこともあります。快適な睡眠を取るために、遮光カーテンや耳栓、アイマスクの活用など、眠るための環境づくりも重要になります。
毎日一定のタイミングで眠るリズムを作ることが、準夜勤生活を安定させるポイントです。
家庭との両立や自分時間の確保はできるか
準夜勤では、勤務開始が夕方という特性上、日中の時間を比較的自由に使えます。これにより、保育園の送り迎えや通院、家庭の用事などとの両立がしやすい点は大きなメリットです。
ただし、一般的な夕食の時間帯と勤務時間帯が重なるため、家族との食事や団らんが取りにくくなる点も考慮しましょう。あらかじめ家族と生活のリズムをすり合わせる、食事の支度を先に済ませておくなど、家庭内での段取りも働きやすさに影響します。
工場勤務でのタイムスケジュール事例
工場勤務での準夜勤のスケジュールは、次のような流れで構成されていることが一般的です。
- 14:30:工場入り・タイムカード打刻
- 14:45:作業着へ着替え・チーム朝礼
- 15:00:作業開始(部品加工・組立・検査など)
- 18:00:休憩(30分〜60分)
- 18:30:作業再開
- 22:00:ライン整備・生産記録の整理
- 24:00:業務終了・帰宅
このように、準夜勤は夕方から夜にかけてのピークタイムをカバーする勤務として位置づけられています。
交代制シフトの「準夜勤→日勤」への切り替えパターン
準夜勤の勤務体制には、固定シフトと交代シフト(ローテーション)の2パターンがあり、交代制の場合は数日〜1週間単位で「準夜勤 → 日勤 → 夜勤」などと勤務時間が切り替わるケースもあります。
このような切り替えの際は、体調管理と睡眠リズムの調整が重要です。特に準夜勤から日勤へ戻る際には、短時間で生活サイクルをリセットしなければならず、疲労が蓄積しやすい傾向も見られます。
食事のタイミングや就寝時間を前倒しするなど、事前に「身体のリズムを切り替える意識」を持つことがポイントです。
準夜勤はきつい?実態から見るメリットとデメリット

準夜勤は、日勤とも夜勤とも異なる中間的な勤務形態として、多くの工場や製造現場で採用されています。ただし、時間帯が特殊であるぶん、その実態は働いてみないとわからないところもあるでしょう。
「身体は慣れるのか」「精神的にきつくないか」「生活リズムをどう保つのか」――こうした不安を抱える人に向けて、実際に準夜勤を経験した人の声や現場の事情をもとに、メリットとデメリットを整理して解説します。
準夜勤のつらさ:体が慣れるまでのリアル
準夜勤でもっとも多く聞かれるのが、「体が慣れるまでが大変だった」という声です。
日勤と違い勤務が夜にかかるため、夕食の時間や就寝タイミングがずれ込むことで生活リズムは乱れがちに。具体的には、準夜勤の初期段階で次のような負担を感じたという声が聞かれています。
- 帰宅が深夜になることで、睡眠の質が下がる
- 家族との生活時間が合わない
- 夕方以降に活動するため、体内時計が乱れやすい
ただし、こうしたつらさは「一定期間で身体が順応する」といった意見も多く、無理のないスケジュール管理と生活習慣の調整によって緩和できます。
準夜勤のメリット:時間の自由度やストレスの少なさ
一方、準夜勤ならではの働きやすさもあります。特に次のような点は、日勤や夜勤と比較した際の明確なメリットです。
- 午前中の時間を自由に使える(役所や病院、保育園の対応など)
- 深夜勤務と比べて身体への負担が軽く、生活リズムを整えやすい
- 通勤時間帯がずれるため、交通機関が混雑しにくい
また、人が少ない夕方以降の時間帯に集中して作業できるため、精神的ストレスを感じにくいという声も多く聞かれます。「日中より静かで作業に集中できる」「人付き合いが苦手でも働きやすい」という意見は、特に工場現場では共感を得やすいポイントです。
準夜勤のデメリット:夕方以降の予定が立てにくい
メリットの一方で、夕方以降のスケジュールが制限されるというデメリットは無視できません。
- 家族や友人と夕食を共にする機会が減る
- 冠婚葬祭や地域の集まりなど、夕方〜夜のイベントに参加しにくい
- 子どもとのふれあい時間が短くなる可能性がある
このように、家庭やプライベートとの両立を重視する場合、準夜勤が不向きになるケースも考えられます。とはいえ、午前〜午後の時間帯が自由に使えるため、生活スタイルを工夫すればカバーできる部分もあるでしょう。
製造業ならではの「準夜勤のきつさ」
工場や製造現場での仕事に特化して考えたとき、準夜勤には現場特有の負担もあります。
- 立ち仕事が多く、身体に疲労が蓄積しやすい
- 工場内の騒音や温度環境によって集中力が求められる
- 深夜にかかる作業は安全面への注意も必要
特に安全面には要注意です。夜間は判断力が鈍りがちで、事故リスクが上がることも考えらえます。
その一方で、「仕事の内容が決まっていて迷わない」「繰り返し作業に集中できる」といったように、仕事に慣れた人ならではの快適さも存在します。
準夜勤で支給される手当と給与水準
準夜勤で働くうえで、「給与はどのくらいになるのか」「夜勤手当はつくのか」といった金銭面も多くの人が気になるポイントでしょう。
特に工場勤務の場合、基本給に加えて各種手当がどのように支給されるかは、生活設計や就業判断に大きな影響を与えます。準夜勤に関する代表的な手当の種類や相場感、実際の給与モデル、さらには求人票でのチェックポイントについて確認していきましょう。
準夜勤での手当の相場と支給条件
まず確認しておきたいのは、「準夜勤」という勤務に対して、必ずしも一律の手当が法律で定められているわけではないという点です。
法律上、22:00〜翌5:00の勤務には深夜割増(通常の25%以上)が義務付けられていますが、それとは別に「夜勤手当」「交代勤務手当」などを支給するかどうかは、各企業の就業規則によって異なります。
- 深夜割増:労働基準法により定められた「22時〜5時に働いた場合、通常賃金の25%以上を上乗せする」という法定の割増賃金。支給は義務
- 夜勤手当:企業が独自に設定する追加の手当(例:1勤務につき1,000円など)。支給の有無や金額は会社ごとに異なる
準夜勤では、次のような支給パターンが一般的です。
- 22:00以降に勤務がかかる場合は深夜割増の対象
- 企業によっては、独自に「準夜勤手当」や「交替手当」が支給されるケースもある
- 時間帯によっては、夜勤手当がつかないこともある(例:15:00〜22:00)
勤務時間帯によって深夜割増、そして企業が独自に設定する追加手当である「夜勤手当」の対象可否が変わる点がポイントです。夜勤手当の取り扱いは就業先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
準夜勤の給与モデルケース
あくまで一例ですが、製造業の現場で準夜勤を行う場合の想定モデルケースを見てみましょう。
| 項目 | 日勤(8:00〜17:00) | 準夜勤(16:00〜0:00) |
|---|---|---|
| 基本給 | 200,000円 | 200,000円 |
| 深夜割増 | - | 約5,000円(22時〜0時) |
| 準夜勤手当 | - | 3,000円(企業規定) |
| 月収合計(概算) | 200,000円 | 約208,000円〜210,000円 |
このように、同じ基本給でも深夜帯の勤務が含まれることにより、割増や手当で月収が上がるケースが一般的です。ただし支給の有無や金額は勤務先によって異なるため、あくまで目安として認識してください。
就業前に確認すべきポイント
手当や給与に関するトラブルを避けるために、就業前には次の点を明確にしておきましょう。
- 勤務時間帯に22:00以降が含まれているか
- 深夜割増や夜勤手当の支給条件(何時から何時まで対象か)
- 交代勤務手当や準夜勤手当の有無
- シフト制の場合、手当がつくシフトとつかないシフトの違い
求人票では、「手当あり」とだけ書かれて詳細が明記されていないこともあります。その場合は、面接や面談時に「具体的な手当の金額や条件を教えてください」と確認することが大切です。
工場勤務での準夜勤手当の実例
実際の求人では、以下のような記載がされていることがあります。
- 「準夜勤手当:1勤務あたり500円支給」
- 「22時以降は深夜割増25%加算」
- 「交代勤務手当:月5,000円(交代制勤務者のみ)」
- 「深夜手当とは別に、準夜勤手当として1日400円」
このように、「深夜割増+独自手当」の組み合わせで構成されているケースが多いです。ただし、すべての企業が準夜勤に特別な手当を設けているわけではありません。事前の確認は必須です。
求人票の「手当条件」の見方【工場系求人の場合】
工場系の求人票を読む際には、以下の記載をチェックしましょう。
- 「シフト制(夜勤あり)」の記載 → 時間帯の確認を
- 「各種手当支給」 → 内容の詳細を質問する
- 「深夜手当あり」「交代勤務手当支給」などの有無
- 月収モデルに手当が含まれているか(含む/含まない)
また、「月収例」に手当が含まれている場合は、どの条件での支給か(フルシフト?準夜勤?)を確認します。求人情報だけで判断せず、実際の働き方と収入のバランスを理解しておくことが、後悔のない就業選択の第一歩です。
準夜勤に向いている人・向いていない人
準夜勤は、「夜勤よりラクそう」「でも日勤と違って生活が不規則になりそう」――そんな印象を持たれがちな勤務形態です。しかし実際には、体質やライフスタイル、家庭環境などによって向き・不向きが分かれます。
ここでは、準夜勤に向いている人・そうでない人の特徴を整理し、自分自身がどちらにあてはまるのかを考えるヒントを提供します。あわせて、事前に備えておきたい準備や習慣づくりについても解説します。
準夜勤に向いている人の特徴
準夜勤は、次のような傾向の人にとって、比較的ストレスなく取り組みやすい勤務形態です。
- 朝が苦手で、昼頃から活動するのが得意なタイプ
- 平日午前中に役所・病院・銀行などへ行く用事が多い
- 家庭内で夕方以降の時間をあまり必要としない
- 自分のペースで過ごす時間を重視したい
- 混雑を避けた通勤や、静かな作業環境を好む
特に製造業・工場勤務では、「夜勤は体力的に不安だけど、日勤より融通がきく働き方がいい」という層にとって、準夜勤はバランスの取れた選択肢となるでしょう。
また、製造現場において、準夜勤に向いている人には次のような傾向も見られます。
- 単純作業や繰り返しの業務に集中できる
- 体を動かすことに抵抗がない(立ち作業が多いため)
- 静かな時間帯での作業を好む
- チーム作業よりも個人作業に安心感を持てる
- 「黙々とこなす仕事」が得意
このような特徴に合致する人は、準夜勤の現場でも高いパフォーマンスを発揮しやすく、仕事のストレスも軽減されやすいといえるでしょう。
準夜勤に不向きな人の傾向
一方で、次のような人は、準夜勤にストレスを感じる可能性が高いです。
- 規則正しい生活を重視しており、夜は完全に休みたい人
- 家族との夕食や夜の時間を大切にしている人
- 夜に外出・通勤することに不安を感じる人
- 睡眠環境に敏感で、日中にしっかり眠ることが難しい人
- 子どもの就寝・食事時間と勤務時間が重なりやすい家庭環境の人
とくに家庭と両立したい人にとっては、夕方〜夜の家庭内での役割と勤務時間がぶつかることが大きな課題になります。就業前に家族と生活リズムをすり合わせておくことが重要です。
まとめ
準夜勤は、日勤とも夜勤とも異なる「中間的な勤務形態」として、工場や製造業を中心に多くの職場で採用されています。
夕方から深夜にかけて働くため、日中の時間を自由に使える一方で、生活リズムの調整や家庭との両立には工夫が必要です。勤務時間や給与体系、そして身体への負担などの要素をふまえ、自分のライフスタイルや働き方に合っているかどうかを見極めましょう。
就業前に実態を理解しておくことで、納得のいく選択と、長く続けられる働き方につながるでしょう。
工場・製造業のお仕事探しは求人サイト「e仕事」がおすすめ!
工場・製造業のお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事」がおすすめ!
例えば
- 時給1900円以上
- 月収35万円以上
- 寮費無料
- 大手メーカー求人多数
など様々な求人があります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。
e仕事はこちらから↓↓↓
関連記事
求人カンタン検索
こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。
都道府県で探す
業種で探す
こだわり条件で探す
- 待遇
- 働き方
- 募集条件
- 職場環境